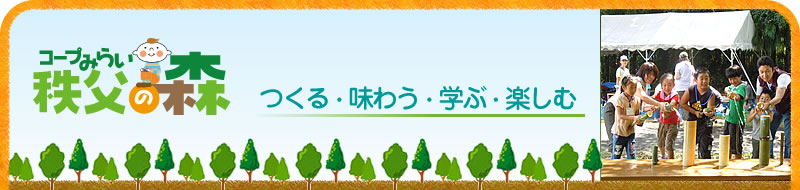つくる・味わう・学ぶ・楽しむ
一年間を通して、四季折々の自然を満喫しながら、様々なイベントを実施しています。2012年過去の記事
12月1日(土)参加者30人で「自然のめぐみでものづくり~クリスマスリースづくり~」を行いました。
森をひとまわりしながら、リースづくりの材料となるクズを見つけ、クズの生態や駆除の必要性についてスタッフから話を聞きました。竹林や傾斜地に自生しているクズを採集し、輪に整え思いおもいの大きさのリースを作りました。リボンや松ぼっくりなどを装飾し、色とりどりのリースを完成させました。
参加者からは、「初めて手づくりでリースを作りました。クズのつるを取るところから行い、満足のいく完成品が出来ました」「森の説明もしてもらえて、森を守ることの大切さも知ることが出来ました」などと感想が寄せられました。
コープ秩父の森のボランティアさんが所有している雑木林から、太さ20センチメートル程のコナラの木を講師の方の指導のもと切り倒し、90センチメートルに切り揃え、52本のホダ木を作りました。
ホダ木は乾燥させ、2月にシイタケのコマ打ちに活用します。
参加者からは、「紐の結びかたやしまい方など実生活でも使える方法を教えていただき、とても勉強になりました」「初めての体験でしたが、作業の説明が分かりやすく、大変有意義でした」
森を散策しながら、自然に関するクイズの答えを探し出しました。秩父在住の草笛名人のご協力で、柿の葉の王冠や人形、オナモミやモミジのブローチ、彼岸花のネックレス、シュロの葉を編んだバッタなどを、秩父の草花を題材にして作りました。
昼食後、生きものさがしを行い「コロコロ」と鳴くエンマコオロギや赤とんぼを虫かごに入れ、体の特徴や生態などを図鑑で調べました。
参加者からは、「子どもとともに自然に触れ合う事ができ、楽しませてもらいました。いろいろなことを教えていただき、大変勉強になりました。」との感想が寄せられました。
最初にイベント広場で草の上を虫とり網でなでて、網の中に入る虫を観察しました。コオロギやバッタがたくさん網に入り、図鑑で名前を調べたり、鳴き声を聞いたりしました。
また、ススキの野原では、イトトンボやアキアカネなどのトンボを見つけ、冬の越し方や成長の仕方などを学習しました。
4月に植えたユズの葉を捕食しているアゲハチョウの幼虫も発見しました。
参加者からは、「いろいろな種類の昆虫を観察でき楽しかったです。身近な昆虫にでも、知らない事がたくさんありました。子どもたちと一緒に参加できよかったです」
「珍しいトンボを探せて、嬉しかったです」との感想が寄せられました。
8月31日、9月1日、3地区のエリア会(南部、東南、コープ吹上・深谷FFC)主催のコープ秩父の森教室に76人が参加しました。
参加者は、森の管理保全の話を聞いた後、バターナイフや水鉄砲づくりに挑戦しました。森にしかない宝物を探すネイチャーゲームや火おこし体験なども行い、夏休み最後の週末を家族そろって楽しみました。
参加者からは、
「竹を間伐するなど、普段体験できないことだったので、親子ともども楽しめました」(東南)
「バターナイフづくりは少し難しかったけれど、大切にしたいです」(南部)
「自然の中で草木の名前や豆知識を教えていただいて勉強になりました」(コープ吹上・深谷FFC)
などと感想が寄せられました。
コープ秩父の森を散策しながら、花の周りに集まるチョウやアブを見たり、植林したコナラやクヌギの成長の様子を観察したり、私達が出来る豊かな森づくりの取り組みなどをクイズ形式で学習しました。
その後、細めの竹を切り倒し、折り紙や短冊で飾り付けをし、旧暦の七夕飾りを楽しみました。
参加者からは、「森の中のいろいろな生きものや植物を観察しながら探検し、自然に触れることが出来ました。クイズを出していただいたので、忘れていたこと、知らなかったことなど学べてよかったです。」などと感想が寄せられました。
7月21日(土)コープ秩父の森ボランティアを含む13人でトンボの池づくりと草刈りをおこない、たくさんのトンボが集まることができるようにしました。
水辺の周りの草刈りをおこなった後、スコップで池を広げ、粘土質の土で、底から水が染み出さないようにしました。今後雨が降って水が溜まるのを待ちます。
参加者からは「粘土遊びのようで楽しかったです。」と感想が寄せられました。
6月30日(土)午前中の竹の水鉄砲づくりに続いて「生きものさがし」を開催し、6人の参加で草刈りをしたススキの野原などで、隠れている昆虫やチョウなどを探しました。
ツチイナゴやオオカマキリ、ルリシジミなどを見つけ観察しました。また、間伐しておいた竹からベニカミキリムシも発見し、竹が食べ物になることを学習しました。
参加者からは、「虫を捕まえたり、虫の観察ができてよかったです。またやりたいです。」「普段見られない虫、植物が発見でき、図鑑で調べられてよかったです。」との感想が寄せられました。
6月30日(土)間伐をした竹を使った水鉄砲づくりに子ども3人を含む6人が参加しました。
参加者は、豊かな森づくりには竹林の管理が大切なことなどの話を聞いた後、のこぎりや小刀の使い方を教わり、水鉄砲をつくりました。
初めて竹を切る参加者も多く、ぎこちない手つきでしたが少しずつ慣れて、竹の太さを変えたり、水が遠く飛ぶように布の厚みを工夫しながら、水鉄砲をつくりました。つくった水鉄砲で的あてをして楽しみました。午後は「生きものさがし」をおこないました。
参加者からは、「竹を切るところから体験できたのは良かったです。」との感想が寄せられました。
雨がふったりやんだりする中、参加者は大まかな作り方の説明を受けた後、切り出した竹にドリルやキリで穴を開け、それぞれの竹の節の位置や太さ、長さなどを考慮しながら、竹のクギで固定したベンチを作りました。
その後、参加者全員で、竹垣づくりを行い、昨年10月に作った竹垣を延長しました。
参加者からは、「久しぶりにノコギリとナイフを使い、楽しくベンチづくりができました。」「思い描いていたものとは少し違うものでしたが、素敵なベンチが出来上がりました。」「竹垣の作り方に感心しました。」と感想が寄せられました。
クイズをしながらコープ秩父の森を散策した後、秩父在住の草笛名人のご協力で、普段何気なく見過ごしている草花や自然に眼を向け、タンポポの茎や葉っぱを使った笛、ホウの葉を使ったキツネの面、シュロの葉を編んでカゴつくりなど自然体験あそびを行いました。
昼食後、生きものさがしとネイチャーゲームを行いました。
参加者からは、「虫やチョウなど初めて見て観察するなど、子どもとともに大変勉強になりました。」「葉っぱでこんなに遊べるなんて驚きしました。」との感想が寄せられました。
3月17、24、25日コープ秩父の森(秩父市)で3地区(中部地区、西北地区、南部地区)が主催し、のべ118人が参加しました。
火おこし体験では、遠心力で棒を回転させ摩擦の力で火をおこしました。マッチやライターを使わず火をつけることの大変さと火がつく喜びを学びました。ついた火でかまどに火をつけ、豚汁やお茶、スープなどを味わいました。
参加者からは「火おこしは初めての体験でした。難しかったけれど、火がついてよかったです。」「あと少しで火がついたので残念でした。」などの感想が寄せられました。
ネイチャーゲームでは、「カモフラージュ」をテーマに自然の中に隠しておいたおもちゃや紐などを探し出すゲームを行いました。枯れ葉や土の上に置かれた同じような色や形のものは見つけにくく、 動物が周囲の植物や環境にそっくりな姿をすることで敵から発見されない仕組みなどを学びました。
参加者からは「ネイチャーゲームは子どもよりも大人が夢中になって楽しんでしまいました。」「自然に触れあえてよかったです。」などの感想が寄せられました。
2月25日、参加者6人で生きものしらべを行いました。
早朝に雪が降り、気温は2度の寒い中、森の中では鳥が「ギーギー」と鳴いていましたが、簡単には姿を見せてくれませんでした。そんな中でも、注意深く森を探索すると、山モミジの木の下でツチグリ(きのこの仲間)を発見。指で押すと白い胞子が舞い上がりました。
また、植林したクヌギの枝にオオカマキリの卵のう(卵を守る袋)も発見することができました。
参加者からは「今まで見たこともないきのこが見られて良かったです。虫はあまり見られなかったので、生き物が活発に動き出したころまた参加します。」と感想が寄せられました。
2月25日、参加者13人で、昨年11月から3ヶ月乾燥させたシイタケのホダ木(*)に、15センチメートル間隔に穴を開け、木槌を使ってシイタケ菌が白く浮き出ているコマを埋め込みました。
コマ打ちしたホダ木は、コープ秩父の森の一角に、湿度や温度が保てるよう参加者が力を合わせて井桁に積み上げました。
参加者からは「思ったより簡単にコマ打ちができました」などと感想が寄せられました。
コマ打ちしたしいたけは、夏を2回越した後、収穫できるようになります。
(*)ホダ木:シイタケを栽培する木のこと
1月22日「冬の生きものしらべ」を開催し、3人が参加しました。
2日前からの雪で、積雪10センチメートルの銀世界となった会場には、ノウサギやタヌキと思われる足跡をあちらこちらに見つけることができました。
雪を掘るとタンポポなどの草花がぴったりと地面にはりついて、じっと寒さに耐えている姿が確認できました。
自然の中の色探し(ネイチャ-ビンゴ)では、冬枯れの中でも様々な色があることが分かりました。 また、準絶滅危惧種に指定されているカヤネズミの巣も発見できました。詳しくはこちら
参加者からは、「コープ秩父の森では、多種多様な植物や動物が棲息していることが分かりました。」「動物や植物は、様々な工夫をしながら寒い冬を過ごしていることがよく分かりました」などと感想が寄せられました。